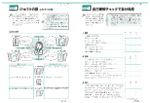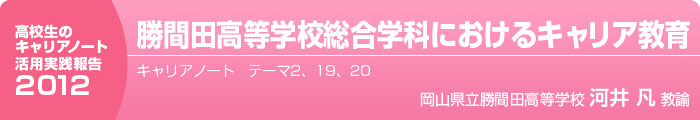

岡山県の北東部(勝田郡勝央町勝間田)、津山市と美作市の間に位置する勝間田高等学校は、「質実剛健」の校訓のもと、勉学と部活動の両立を目指し、生徒が明るく積極的な高校生活を送っている。総合学科の他に、グリーン環境科、食品科学科、産業工学科の4つの学科があり、農業系の専門学科がそれぞれに設備を持っていることを生かし、「食品製造」や「林産加工」などの科目があるという特色を持つ。岡山県北部には山間地域が多く、公共機関などの利便性が低い環境の中でも、勝央町及びその周囲の広範な地域から生徒が集まってくる。
田園地帯の広がるこの地域は農業が盛んで、特産品の黒大豆「作州黒」は、高品質で全国2番目の生産量を誇る。また、自動車を使えば大阪(吹田)より約2時間というアクセスには恵まれていることから、勝央町内や近隣の市・町には計5ヶ所の工業団地があり、ここでは多くの卒業生が地域産業を担っている。
勝間田高等学校では、独自の「進路の手引」をもとに、社会に向けて積極的に働きかけることのできる人材育成を目指したキャリア教育への取り組みが行われている。
◆本校の特色と進路
 本校は、総合学科、グリーン環境科、食品学科、産業工学科の4学科からなり、総合学科においては、4つの系列からひとつを選択すると同時に、自由選択科目を設け、2年次から自分自身の個性、能力などを伸ばすことができるようにしている。1年次で全員を対象としたインターンシップを実施し、2年次、3年次での総合的な学習の時間は、キャリア教育に濃く関わる内容が中心となっている。
本校は、総合学科、グリーン環境科、食品学科、産業工学科の4学科からなり、総合学科においては、4つの系列からひとつを選択すると同時に、自由選択科目を設け、2年次から自分自身の個性、能力などを伸ばすことができるようにしている。1年次で全員を対象としたインターンシップを実施し、2年次、3年次での総合的な学習の時間は、キャリア教育に濃く関わる内容が中心となっている。
本校の進路状況は、最近3年の傾向として、就職希望者が増加し、70%近くの生徒が就職希望である。地元志向が強く、就職者のうち約80%が地元(自宅通勤可能な地域)に就職している。かつては地元での就職といえば、地域の工業団地を中心とした製造業への就職が70%に近かった。しかし、2008年のリーマンショック以降は製造業の求人が激減し、ここ1,2年は50%弱に留まっている。一方、サービス業や医療福祉(介護職)への就職が増加し、これら2つを合わせると、就職者の30%を超えるようになった。
進学希望者は全体の30%程度である。専門学校進学が多く、看護・介護、調理、自動車整備等実学志向が強い。卒業後は地元(県内)に帰ってくるつもりで進学する者が多い。
進学者の大半はAO又は推薦入試による受験であるため、就職・進学共に12月末には90%前後の生徒の進路先が決まっている。大部分の生徒にとっての進路決定(受験)の時期は8〜11月あたりである。
生徒は明るく素直で純粋な者が多いが、勉強に苦手意識を持っている者が少なくない。
自己肯定感を高め、視野を広げ、自らの進路を自らの力で切り開いていこうとする積極的、主体的な姿勢を養っていく必要がある。また、大部分が本校卒業後即社会に出るため、社会人として必要な知識・技能・マナー等の定着を目指し、日々の指導にあたっている。
◆キャリア教育に関わる本校の主な取り組み<総合学科におけるキャリア教育年間計画>
〈「キャリア教育で育てたい能力」に対する本校の具体的な取り組み〉
| ①人間関係形成・社会形成能力 *インターンシップ *進路LHR活動 ・アサーティブトレーニングなど ・コミュニケーションスキルズなど *マナー講習会 *各種学校行事 *総合的な学習の時間 ・ヒューマンスキル演習など |
②自己理解・自己管理能力 *インターンシップ *進路ロングホームルーム活動 ・自己発見、自己PRスキルズなど *総合的な学習の時間 ・各種発表など |
| ③課題対応能力 *進路ロングホームルーム活動 *総合的な学習の時間 ・進路先の研究など |
④キャリアプランニング能力 *インターンシップ *社会人講話 *進路ガイダンス *上級学校訪問 *進路ロングホームルーム活動 |
本校では、1、2年次で行う「進路学習ホームルーム」のテキストとして、独自のワークシートや資料を載せた「進路の手引」を作成している。1、2年次のうちに、計画的に高校生活を送るためのガイドとなるよう、年次ごとにやるべきこと2年分を1冊にまとめ、全学科の生徒に配布している。1冊にまとめることで、生徒・担任共に長期的視野が養われ、3年間を見据えた活動ができると考えている。また、その他の進路に関する資料等は「進路ファイル」へ綴じていくようにしており、必要に応じた振り返りをすることに役立っている。
<進路の手引き概要> 総合学科は、インターンシップにおけるコミュニケーション能力の育成にも力を入れている。職業体験を通して、仕事の意義や役割を理解し、望ましい職業観・勤労観を身につけることや、地域産業や職場の実態に触れ、進路選択に対する理解を深めることを目的として行っている。長年おこなっているインターンシップだが、生徒の強い希望により、平成23年度から実施した5〜10日間の長期インターンシップは、授業ではわからない大変さや将来就きたい仕事への意欲が高まったと感じている。
◆キャリア教育のツールとして「高校生のキャリアノート」の活用
本校では、独自の「進路の手引」をテキストとして使用し、キャリア教育・進路学習をすすめてきた。しかし、これまで使用していなかった『高校生のキャリアノート』には、キャリア教育を進めていくうえで活用したいテーマがあったため、まずは各学年1題材ずつ取り入れることとした。採用テーマは、キャリア教育で育成したい能力として掲げられている①人間関係形成・社会形成能力、②自己理解・自己管理能力、③課題対応能力、④キャリアプランニング能力、それぞれのねらいを伸長させることができることを基準に、次のように選定した。
ねらい:自分とはどのような人間か、自分の特長はどのような点かについて意識させるために。
このテーマには「ジョハリの窓」も採り入れられており、3年間各自が「自分育て」「売りを作る」活動をしていく上で、まず必要となる「自己理解」の指導に有効活用できると考えた。
2年次《テーマ19. 自己PRスキルズ》
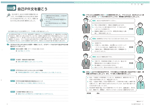 <クリックで拡大>
<クリックで拡大>
ねらい:「自分分析」や「自己PR文」に取り組んでいく上で、考える道筋を立てていくために。
就職試験や推薦入試が近づいてからの取り組みでは間に合わないので、自己理解や自己PRは2年次から指導していく必要があると常々感じていた。
3年次《テーマ20. コミュニケーションスキルズ》
 <クリックで拡大>
<クリックで拡大>
ねらい:全生徒対象に6月上旬、9月上旬に実施する「模擬面接指導」の事前指導として。
進路決定に必要なスキルとして。「話し方」「聴き方」「観方」を分けてトレーニングできるよう編集されているので活用した。
◆成果と課題
アンケートの結果から3つの学年を比較してみると、上級学年ほど課題に対して真剣に取り組む生徒が多くなっていた。特に2,3年生のクラスでは、積極的に質問をするなど、前向きな姿勢が目立った。学年が上がるに従って、進路意識が高まってきているということの表れであろう。
<実施後の担任へのアンケート> また、「段階的に進められるので取組みやすい。」「具体的な場面を想定し、考えやすい。」など、担任からのアンケートの感想にもあるように、活動の中で生徒の考えがまとまり、深まっていったと考えられる。採択したテーマは概ね好評であったので、引き続き同じものを使用したい。指摘のあった問題点は、指導の場面で生かすようにしたい。
一方、時間数の確保がなかなか難しいという現実がある。総合学科は1年次に「産業社会と人間」で2単位、3年次に「総合的な学習の時間」で2単位があるが、農業学科ではその何れもない。(総合的な学習の時間3単位のうち、2単位は課題研究で代替しているため)従って、全学科で実施するためには進路学習ロングホームルーム年間計画を見直して、時間を確保する必要がある。実施計画の検討も進めながら、当面は各学年1テーマを利用していきたい。
実施時期については、2年次の〈19.自己PRスキルズ〉は、今年度と同時期で妥当と考えられるが、1年次の〈2.入門 自分発見〉、3年次の〈20.コミュニケーションスキルズ〉は、学年団と協議し、早い時期に決定したいと考えている。
◆本校の目指したいキャリア教育
産業教育懇談会等で企業の方々の意見を聞くと、「自ら働きかける力」「情報発信力」が強く求められていることがわかる。本校の生徒たちは、ともすれば「井の中の蛙」になりがちな環境にあり、「おとなしい」「指示待ち傾向」という評価を受けることが多い。そのため、本校ではこれまでも「ボランティア活動」「異校種間交流事業」「文化祭」等で、生徒が学校外の人たちと交流する事業に力を入れてきた。これらをベースにして、積極的に外に向けて働きかけることのできる人材を育てていきたいと考えている。
 長期インターンシップも、生徒たちの目をより外に向けさせる仕掛けの一つである。インターンシップを経験する中で、生徒は特定の仕事のスキルや人間関係以外に基礎学力の必要性にも気付いていく。基礎学力の伸長は、卒業後に各人がキャリア形成を図っていくために必要不可欠であり、早い機会にこのような経験をすることは、大変有意義なことである。今後、長期インターンシップへの参加者を増やしていく取り組みを進めたい。
長期インターンシップも、生徒たちの目をより外に向けさせる仕掛けの一つである。インターンシップを経験する中で、生徒は特定の仕事のスキルや人間関係以外に基礎学力の必要性にも気付いていく。基礎学力の伸長は、卒業後に各人がキャリア形成を図っていくために必要不可欠であり、早い機会にこのような経験をすることは、大変有意義なことである。今後、長期インターンシップへの参加者を増やしていく取り組みを進めたい。
キャリア教育の充実は、魅力ある学校作りにつながると考える。今後も各取り組みの見直しを図りながら、キャリア教育の質を高めていきたい。